【クチコミ商品情報】【お得サイズ】フラクトオリゴ糖(FOS)1000mg

フラクトオリゴ糖類は、他の砂糖類と違って消化液によって分解されず、おなかまで届きやすく、ビフィズス菌などの善玉菌が必要とする栄養となります。
また、フラクトオリゴ糖のカロリーは通常の砂糖の約半分程度という特徴を持っています。
おなかの菌のバランスは私達の健康を左右するほど大事です。 食物で善玉菌を食べても、おなかが適切な環境でないと、どんどんとその数が減ってしまいます。
フラクトオリゴ糖で善玉菌を増やし、腸内環境を整えて快適な日々を!
【お得サイズ】フラクトオリゴ糖(FOS)1000mg Source Naturals社
100粒(タブレット)
※約25~33日分
■2,290円(税込)
商品のクチコミ
クチコミはあくまでも個人的な感想です。体感には個人差があります。
| 50代 / 男性 2024/05/04 |
|
これは便利!
リゴ糖の摂取には液状か粉状が定番ですが、今回タブレットがあると知り早速試してみました。
以前は口に合わなくても飲み物に無理やり混ぜて服用していましたがタブレットだとそういった面倒もストレスもなく本当に助かります!
お腹の調子も良くなりましたし言うことありません。
|
| 50代 / 男性 2020/01/22 |
|
以前は
以前はパウダータイプを使っていたのですが、私にはタブレットタイプが使いやすいようです。
乳酸菌へのご馳走として。
|
| 30代 / 女性 2016/06/14 |
|
アシドフィルス菌と一緒に
オリゴ糖に中でも乳酸菌に一番効果的なフラクトオリゴ糖、粉タイプだと細かい粉が飛んだり湿ったり扱いにくいですが、これは錠剤。
アシドフィルス菌と一緒に飲んでいます。
|
商品詳細

・FOSは、善玉菌のエサになり、善玉菌と悪玉菌のバランスをサポートします。
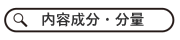
(4粒あたり)
◆エネルギー 10kcal
◆総炭水化物量 4g
・食物繊維 4g
◆FOS(フラクトオリゴ糖) 4g
◆ナトリウム 25mg
◆鉄(天然由来) 450mcg
(その他成分)
◆ステアリン酸 、変型セルロースガム 、コロイダルニ酸化ケイ素 、ステアリン酸マグネシウム
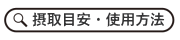
●Daily valueは定められていません。
・栄養補助食品として1日3~4粒を目安にお召し上がり下さい。
※摂取目安はラベル表記を和訳しております。
"Daily value"とは、FDA(米国食品医薬品局)によって推奨される一日の摂取量のことです。
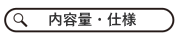
100粒(タブレット)
※約25~33日分
※ベジタリアン仕様
※低アレルギー性
主要配合成分詳細
【フラクトオリゴ糖とは】

オリゴ糖は、母乳中に含まれているビフィズス増殖因子と呼んでいた物を研究した結果、それがオリゴ糖である事が判明したといわれています。その後、数々の研究を経て様々なオリゴ糖が発見されました。
このような、腸内善玉菌を増やす働きがある物質をプレバイオティクスと言い、ガラクトオリゴ糖(GOS)やフラクトオリゴ糖(FOS)、マンナンオリゴ糖(MOS)などの種類が知られています。
フラクトオリゴ糖(FOS)はアスパラガスやタマネギ、ニンニク、ゴボウなどの野菜類に含まれており、他のオリゴ糖と同様に消化し難い性質を持っています。
ビフィズス菌は糖分をエサとして増殖するのですが、普通の砂糖やブドウ糖は小腸で消化吸収され、ビフィズス菌のいる大腸にまで届きません。
しかし、フラクトオリゴ糖は人間の消化液では分解されないれないため、小腸では吸収されず、大腸にまで届くことができます。したがってフラクトオリゴ糖はビフィズス菌が増えるための貴重な栄養源になるのです。
また、フラクトオリゴ糖(FOS)は、カルシウムの吸収を促進する働きや、コレステロール値を低下させる働きもある優れものなのです。
[腸内フローラのお話]
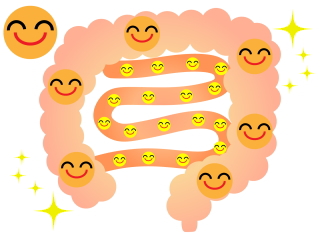
私たちのおなかの中、特に大腸には数百種類、100兆個以上の細菌が棲んでいるといわれています。
その中には、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌や悪い働きをする悪玉菌および日和見菌がいることが知られています。
これらを「腸内フローラ」と呼び、人それぞれに異なった特徴を持っており、その人の健康を左右しているといわれています。
ところが、食生活の偏重や加齢とともに腸内の善玉菌が減ることが知られています。
とりわけ、肥満の人には「バクテロイデス属」と呼ばれる「短鎖脂肪酸」を生み出す腸内細菌が少ない事が、最新の研究で明らかになってきています。
プロバイオティクスと呼ばれる善玉菌や善玉菌の栄養源であるフラクトオリゴ糖などのオリゴ糖をとることで、善玉菌が元気になり、悪玉菌の数や有害物が減り、腸内環境を良好に保つことができます。
善玉菌が優勢な状態を保つ事こそが「良好な腸内環境」といえます。
「腸内環境が良好」であれば、便通などの改善や栄養の吸収がよくなり、ひいてはそれらに係る健康リスクの低減につながると考えられています。


 ブランド紹介★Source Naturals社
ブランド紹介★Source Naturals社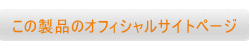

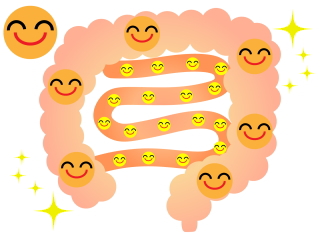

 【お得サイズ】フラクトオリゴ糖(FOS)1000mg Source Naturals社
【お得サイズ】フラクトオリゴ糖(FOS)1000mg Source Naturals社

