【クチコミ商品情報】サイダービネガー(リンゴ酢) ダイエットフォーミュラ

グルコマンナンとグレープフルーツ由来の良質な食物繊維が、体の中をキレイなコンディションにととのえながら、健康的なダイエットをサポートします。
ダイエットを応援するビタミンB6とクロミウムも配合しています。
また、ダイエットサポートではおなじみのケルプ(海藻)はミネラルがたっぷりでダイエット時の栄養補給に役立ちます。
スムーズな流れに役立つレシチンと合わせ、このダイエットサプリメントのキー成分になっています。
サイダービネガー(リンゴ酢) ダイエットフォーミュラ NOW社
180粒(ベジタリアンカプセル)
※約30~45日分
■1,840円(税込)
商品のクチコミ
クチコミはあくまでも個人的な感想です。体感には個人差があります。
| 30代 / 女性 2010/08/28 |
|
お酢好きの母が喜んで飲んでます(笑
自分用に購入したのですが、あまりにも酸っぱい香りがすごくて、何粒か飲んでそのまま飲まなくなってしまいました。
サプリをしまっていた引き出しまで酸っぱい香りになってしまうほどの強力な香りです(笑)。
最近体重増加に悩んでいた母に勧めてみたところ、もともとお酢系が大好きな母なので喜んで飲み始めました。
まだ半分位しか飲んでいないそうなので、今のところまだ実感はないそうですが、リンゴ酢自体は身体に良いものなので、とりあえず最後まで飲んでみると言っていました。
せっかく買ったサプリが無駄にならなくて良かったです(笑)
|
| 30代 / 女性 2009/03/28 |
|
香りが強烈
カプセルインにもかかわらず、香りが強烈です。
「リンゴ酸!」と強調してるサプリです(笑)
以前、3か月くらい飲んでましたが、ハッキリとした効果は私は感じられませんでした。
一緒に飲んでいた友人は、「ダイエット効果が出た!2か月で4キロ痩せた!」って喜んでました。
この友人もリンゴ酸のにおいはすごいねって言ってましたが、気にはならなかった模様。
|
| 10代 / 男性 2009/01/27 |
|
減量に役立ってます。
最近体重を落とすつもりでジムに通っています。
初めは軽く走るだけで結果が出なかったのですが、リンゴ酢ダイエットが良いとトレーナーさんい聞いたので、リンゴ酢を摂取しながら同じ運動をしていたのですが、かなり体重は落ちました!!!!
三週間で1kg!!!!!
夏まで続けます♪
|
商品詳細

・心血管機能の健康をサポートします。
・健康的な体重維持をサポートします。
・健康的な糖代謝をサポートします。
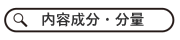
(2粒あたり)
◆アップルサイダービネガー(リンゴ酢)パウダー 500mg
◆大豆レシチン 200mg
◆グルコマンナンファイバー(塊茎) 100mg
◆ケルプ(海藻) 74mg
◆グレープフルーツファイバー 30mg
◆ビタミンB6(ピリドキシンHCI) 7mg
◆クロミウム(アミノ酸キレート) 200mcg
(その他成分)
◆ゼラチン(カプセル)、マルトデキストリン、食物デンプン、シリカ、野菜由来ステアリン酸マグネシウム
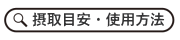
●Daily valueは定められていません。
・栄養補助食品として1回2粒を、1日2~3回、食事と一緒のご摂取をおすすめします。
※摂取目安はラベル表記を和訳しております。
"Daily value"とは、FDA(米国食品医薬品局)によって推奨される一日の摂取量のことです。
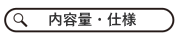
180粒(ベジタリアンカプセル)
※約30~45日分
※ベジタリアン/ビーガン仕様
※非遺伝子組換え(Non-GMO)
主要配合成分詳細
【アップルサイダービネガー(リンゴ酢)とは】

リンゴ酢に含まれるリンゴ酸やクエン酸には、疲労物質である乳酸の生成を抑制、分解しエネルギーに変える働きがあるため、疲労の蓄積を防ぎ、疲労の回復を早める働きがあります。
また、リンゴ酢には、エネルギー代謝を促進させて余分なカロリーを燃焼させる働きがあります。
さらに、カロリーを体内に蓄積してしまう体質を改善するともいわれています。
このことから、ダイエットにもよく用いられ、人気があります。
他の酢と比較して、リンゴ酢にはカリウムが多く含まれており、塩分の排出を助けてむくみを防ぐ働きも期待できます。
総合的には、脂肪を貯めずにサラサラのメグリを促進し、疲労からのリカバリーをサポートする、優れた働きがあります。
【レシチンとは】

レシチンとはホスファチジルコリン(リン脂質の総称)のことで、体内で神経伝達物質のアセチルコリンの原料になります。
アセチルコリンは、加齢に伴う脳の老化を遅らせたり、脳や神経の病気を防ぐなど、老人性認知症のリスクを遠ざける働きがあるとされています。
また、レシチンには脂を水と乳化させる働きがあるため、脂質代謝が活性化され、成人病の予防、肥満解消につながるとされています。
その他、新陳代謝を促し、細胞から老廃物を排泄させ、若さを保つ働きがあるとも言われています。
【グルコマンナンとは】

グルコマンナンは、こんにゃくに含まれる水溶性の食物繊維で、グルコースとマンノースがおよそ2:3の割合で結合したものです。
グルコマンナンは水分を吸って大きく膨張するため、摂取することによって胃の中で膨らみ、満腹感を与えるほか、腸内細菌で分解されるとオリゴ糖ができ、オリゴ糖がビフィズス菌のエサになって腸内環境を整え便通を良くする働きがあるとされます。
また、近年ではグルコマンナンにコレステロールや血糖値を下げる働きがあることが明らかにされており、生活習慣病の予防にその働きが期待されています。
【ケルプ(ブラダーラック)とは】

ケルプ(kelp)とは、コンブ科に属する大きな海藻類をまとめて呼ぶ通称のことですが、特に、カリフォルニア沖の太平洋に生息する巨大な海草「ジャイアントケルプ」を指す場合が多いようです。
ケルプにはヨウ素や亜鉛、マグネシウムなどのミネラル類、多糖類のフコイダン、アルギン酸などの食物繊維が豊富に含まれています。
亜鉛は100種類以上の代謝酵素の構成要素となる必須ミネラルで、たんぱく質や糖質、脂質の代謝に関与しています。
また、ケルプに含まれているアルギン酸は水溶性食物繊維の一種で、腸内で水に溶け込みヌルヌルとしたゲル状となり有害物質を吸着して排出する働きがあります。
食物繊維はヒトの消化酵素で消化されない為、以前までは栄養にならないと考えられていました。
しかし、食物繊維が持つ効用が明らかとなり、今では重要な栄養素として位置づけられています。
【グレープフルーツファイバー (ペクチン)とは】

シトラス(柑橘系果実)の皮には、植物の細胞壁に存在する炭水化物の一種であるペクチンが含まれています。ペクチンは、リンゴやミカンなどの果実や野菜に多く含まれる水溶性の食物繊維です。
オレンジやレモン、グレープフルーツなどの柑橘類にはとりわけペクチンが多く含まれています。
ペクチンは、水を含むと粘度を増す性質があり、余分なコレステや不要物などを吸着して内からスッキリさせると期待されています。
ペクチンは腸内の善玉菌である乳酸菌を増殖させ、腸の調子を整えてくれます。
また、ペクチンは腸内の物質と結合することで便の容積を増やし、腸のぜん動運動を活発にします。
この2つの働きで体内で発生、蓄積した有害物質を体外へ排出するため、特に便通をサポートします。
【ピリドキシン(ビタミンB6)とは】
ビタミンB6 (ピリドキシン)は、たん白質からエネルギーをつくり出す過程で必要な、約100種類の代謝酵素の働きを助ける「補酵素」として、重要な役割を担っています。
ビタミンB6はたんぱく質の代謝に欠かせない栄養素で、たんぱく質の摂取量が多いほどビタミンB6の体内での消費量も多くなります。
最近の日本では食の欧米化が進み、肉類の摂取が多くなったことからビタミンB6の働きが注目されるようになりました。

また、皮膚や粘膜を正常に保ち、神経や血液の働きにも重要な役わりをしています。不足すると、肌が荒れたり、末梢神経の働きが悪くなり手足がしびれたりします。
さらに、ビタミンB6は神経伝達物質の合成にも関わっています。
神経伝達物質とは、脳の神経細胞の間で情報の橋渡しをしている物質で、GABA (ガンマアミノ酪酸)やアルファアミノ酪酸、セロトニン、ドーパミン、アドレナリン、ノルアドレナリンなどがあり、これらが合成される時にはアミノ酸が使われています。
ビタミンB6はアミノ酸の代謝と関わっているため、神経伝達物質の合成を促進する働きがあります。そのため、抑うつ感を感じやすくなったらビタミンB6不足が疑われます。
【クロミウムとは】
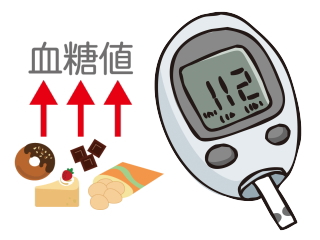
クロミウムはダイエットに活躍する成分としてアメリカで人気に火がつき、糖値レベルのキープや、気になる健康値をととのえる必須ミネラルとして非常に人気があります。
私たちは血中のブドウ糖を細胞内で燃焼させてエネルギーとして生命活動を維持しています。
血中のブドウ糖を細胞に取り込むにはインスリンの助けが必要になります。インスリン不足の状態が慢性的に続いているのが糖尿病です。
体内でアミノ酸、ビタミン、3価クロムが結びついてGTF(ブドウ糖耐性因子)が合成されています。
GTFはインスリンの働きを活性化したり、細胞のインスリン受容体の感受性を上げて、血中のブドウ糖が細胞に上手く取り込まれるようにサポートしています。
このようにインスリンの働きで血中のブドウ糖が細胞内で燃焼されネルギーとして利用されることで正常な血糖値が維持されています。
ところが加齢やストレス、高血糖が長く続いたりするとGTFの材料である三価クロムの体内保有量が不足してきて体内でGTF生産が低下してきます。GTF不足および欠乏が続くと高血糖、糖尿病の発症原因になります。
《参考資料》
日本の食事摂取基準では、クロムの成人1日あたりの目安量10mcgと設定されています。また、耐容上限量は500mcgと定められています。
米国科学アカデミー医学研究所の食品栄養委員会(Food and Nutrition Board:FNB)によるクロミウムの耐容上限量は設定されていません。
また、ピコリン酸クロミウムの吸収率はおよそ1.2%(食物から摂取するクロミウムの吸収率とほぼ同じ)となっています。但し、過剰摂取には注意が必要です。


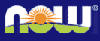 ブランド紹介★NOW社
ブランド紹介★NOW社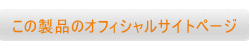






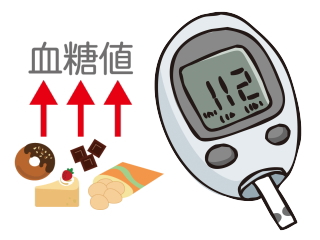

 サイダービネガー(リンゴ酢) ダイエットフォーミュラ NOW社
サイダービネガー(リンゴ酢) ダイエットフォーミュラ NOW社

